宇野常寛著「庭の話」を考える
承認を超えて共在へ:ズレと多様性を包み込む空間の再構想
2011年の東日本大震災以降、日本社会では「絆」が強調される風潮が定着した。それは、災害に見舞われるたびに共同体の再生が叫ばれ、助け合いやつながりの重要性が語られるという、一見すると肯定的なムーブメントである。しかし、その背景には、「つながりを強制される」ことによる息苦しさや、承認を得られなければ居場所を失うという不安が横たわっている。会社における飲みニケーションや、SNS上での相互承認的関係もまた、「評価されること」「特別であること」への過剰な欲望と緊張を生み出している。
宇野常寛の『庭の話』は、そうした現代社会における承認と評価に依存した人間関係の構造を、根本から問い直す意欲的な試みである。本論では、宇野が提起する「庭」という概念を中心に、それが現代のプラットフォーム社会や共同体モデルといかに異なり、いかなる新しい可能性を持つのかを論じたい。また、自身の万博体験や「風の谷」との接続も通して、「庭」が現代社会にとっていかなる希望をもたらすのかを考察する。
「庭」とは何か──評価と承認の外部にある空間
『庭の話』における「庭」という概念は、単なる私有地や園芸空間を指すのではなく、現代社会における新たな“公共空間”の比喩として提示されている。宇野はこの「庭」を、評価や承認に支配されたプラットフォーム社会に代わる空間のモデルとして提示する。その特徴は何か、どのようにそれは従来の社会空間と異なるのか、以下で詳しく見ていきたい。
まず「庭」は、人間と人間の関係だけでなく、人間と“事物”との関係性に重点を置く空間である。たとえば庭には、植物、石、水、虫、気温、時間、風など、多種多様な要素が存在している。これらはそれぞれ異なるリズムや時間感覚を持ち、庭という空間はそれらの“ズレ”をそのまま許容している。人間がそこに手を加えることはできるが、すべてを制御することはできない。つまり、庭とは「完全に管理された空間」ではなく、「部分的にしか関与できない空間」である。
宇野はこれを、現代のSNS空間や共同体とは対照的なものとして語る。SNSは即時性と同期性に満ちており、他者の評価に一喜一憂しながら、アルゴリズムによって“可視化”されることを恐れる空間である。共同体もまた、顔の見える関係の中で“空気”や“同調圧力”が強く働く。どちらの空間にも、過剰な「誰かからの承認」が求められており、そこからの逸脱は容易に“排除”につながる。
それに対して「庭」は、「評価される必要のない空間」であり、「承認を得なくても生きていける空間」である。人はその中で、何者かになる必要がなく、ただ“いる”ことを許される。そこには、社会的役割からも、比較競争からも距離を置いた「存在の余白」が広がっている。
さらに、宇野は「庭」の創造的側面も重視している。庭は、他者との直接的な“つながり”を求めないが、しかし完全な孤立でもない。むしろ、静かな共存や、偶発的な関係性の交差を生む空間として、制作や思索、対話を促す装置である。すなわち「庭」は、“つながらないことで、つながり直す”場所でもあるのだ。
このような庭の性質は、現代の都市空間やネット空間において忘れ去られがちな“公共性”の再構築とも言える。ルールでも制度でもなく、互いの“存在のずれ”を肯定することによって生まれる公共。それが宇野の言う「庭」であり、それこそが現代社会に必要とされる空間なのではないかという問いが、本書の根底には流れている。
コミュニティ構造と「承認」の罠──小・中・大の分断を越えて
『庭の話』で提示される「庭」という空間モデルは、従来の社会に存在するコミュニティ構造の問題点に鋭く切り込んでいる。庭の話を元に「小・中・大サイズ」のコミュニティに分類し、それぞれのスケールにおける承認と評価の構造、そして「庭」がその構造をいかに乗り越えようとするのかを論じてみる。
まず「小サイズ」のコミュニティとは、いわゆる“村”や“町内会”といった、顔の見える人間関係で構成される閉じた空間である。ここでは、共同体の維持が最重要とされ、そのために“空気を読む”こと、“変わらないこと”が美徳とされる。住民同士の距離は近いがゆえに、逸脱した個性は容易に排除され、あるいは無視される。このような空間では、「承認」は制度化されず、あくまで“慣習”や“暗黙の了解”の形で働く。
つぎに「中サイズ」のコミュニティとは、会社、学校、地域団体、医療機関、あるいは自治体のような、組織化された中間共同体を指す。ここでは、公式な評価(査定、推薦、表彰)と、非公式な評価(同調、評判、仲間内のヒエラルキー)が共存する。特に日本においては、形式上の平等性が制度として担保されながらも、実際には“声の大きな人”“空気を作れる人”が影響力を持つことが多い。この構造は、個人が本質的に承認を得ることよりも、共同体に“うまく馴染む”ことを優先させる。
最後に「大サイズ」のコミュニティとは、SNSやオンラインフォーラム、あるいはメディア空間のような、不特定多数が参加可能な匿名的・開放的な空間である。ここでは、アルゴリズムと反応(いいね・リツイート・再生数)が評価の基準を決める。評価は一瞬で可視化され、流行とバズが情報を支配する。そこでは「個人の発信」よりも「群れの中で目立つかどうか」が重視され、発信者は常に「承認のトレンド」に合わせて自己を調整せざるを得ない。
これら三つのサイズのいずれにも共通しているのは、承認と評価が人間関係の中心にあるという点である。そしてそれは、個人の尊厳や創造性よりも、「他者との相対的な位置取り」を優先させる社会構造である。評価されなければ見えなくなる。承認されなければ居場所がない。こうした「生きづらさ」は、時に自己否定を招き、時に他者への攻撃性として現れる。
宇野の「庭」は、こうした構造に対する抜本的な異議申し立てである。「庭」では、人は“役割”からも“パフォーマンス”からも解き放たれる。庭の中では、植物も虫も、岩も風も、互いに影響を与え合いながらも、評価の軸で比べられることはない。ある種の“無関心さ”と“距離”が保たれているからこそ、そこで生まれる関係性は柔らかく、静かで、持続的である。
私はこの視点から、SNSにおける「炎上」や、会社組織における「評価制度の歪み」、あるいは地域共同体における「同調圧力の強さ」がもたらす不健全さを再認識することができた。すべての人間関係を断ち切るのではなく、必要なだけ関わり、余白を保ち、承認に依存しない生を模索する。それが「庭的な空間」における新たな倫理なのではないか。
「風の谷」と「庭」──安宅和人と宇野常寛のビジョン比較
宇野常寛の『庭の話』で提唱される「庭」という概念は、安宅和人が提唱する「風の谷」と多くの点で響き合う。どちらも未来志向的で、「社会をどのように再編成し、人間の尊厳を守るか」という問いに対する応答である。ただし、そのアプローチと立脚点には明確な差異も見出せる。
安宅の語る「風の谷」は、彼の代表的なビジョンの一つであり、ポスト資本主義社会を見据えた包括的な文明の転換構想である。これは、トップダウン的な社会設計、あるいはテクノロジーやイノベーションを活用して「人間中心の社会」を築こうとする試みだ。これに対し、宇野の「庭」は、よりミクロで実存的、感覚的な次元に根ざした構想である。
風の谷は未来の目標であり、「新しい制度のデザイン」を志向する。一方、庭は現在における「生き延びるための環境」であり、制度以前の「空間」=関係性のあり方に注目している。これは「制度/感覚」、「未来/現在」、「全体設計/部分実装」といった対比軸で語ることができる。
また、安宅の風の谷では「良き未来」を見据えた共同体や社会のデザインが志向されるが、そこにはしばしば理念的・普遍主義的な規範が先行する。しかし宇野はむしろ、「あらかじめ共有された正義や理念」の不在を前提に、「異なる価値観を持つ者たちが、互いを抹殺せずに共存できる場」として庭を構想する。そこには一種の「アナーキズム」がある。
両者に共通するのは、既存の共同体(あるいはSNSや国家、企業など)では包摂しきれない人々のための「場」をどう創るかという問題意識である。しかしその答えは、風の谷が制度的変革や教育改革を通じて社会構造そのものを変えることを志向するのに対し、庭は「評価されない時間」「他者とつながらなくても許される空間」といったごく個人的で即自的な実践に重きを置く。
この違いは、ちょうど「都市設計」と「裏庭の手入れ」のような差異である。どちらも人間の生を支えるための営みだが、都市は万人のために設計され、庭は自分や数人のために育てられる。風の谷が人類社会全体を見渡す地図を描こうとするのに対し、庭は今目の前にいる人との関係を大切にし、無理につながらず、評価も強制せず、ただそこに「いてもいい」ことを肯定する。
このように考えると、両者は「上と下」「未来と現在」「制度と感覚」の補完関係にあるとも言える。風の谷があるからこそ、庭が息をつける。庭があるからこそ、風の谷にたどり着ける。この2つのビジョンを重ね合わせることで、我々の社会と個人の両方にとって豊かな空間が開かれていくのではないだろうか。
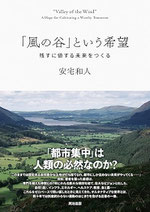
「風の谷」という希望:残すに値する未来をつくる
(安宅和人、英治出版、2025)
EXPO2025と「庭」の体感──多様性と共感の循環構造
「庭」の概念を現実の体験としてもっとも鮮明に感じたのが、私が8回にわたって訪れた2025年大阪・関西万博(EXPO2025)での体験である。
万博は開始前からメディアによる批判に晒され、特にコモンズ型パビリオンに対しては「公民館以下」との揶揄も見られた。しかし、実際に訪れてみると、そこには予想を裏切る豊かな感覚体験と驚きが広がっていた。各国が狭小な空間で展示していたのは、香り、音、織物、映像、そして言葉である。それらは決して「統一感」や「完成されたナラティブ」を目指すものではなかった。むしろ、個々の国が自らの文化と未来を語る試みであり、そのバラバラさが魅力であった。
実はこの「バラバラであるがゆえに魅力的」という構造が、「庭」の姿に近い。
私は万博を訪れるたびに、自身の印象が変化していった。最初は混沌に見えた展示群が、回を重ねるごとに「多様性の祝祭」としての意味を帯びてくる。その中心にある「大屋根リング」が、それらを包み込む大きな「枠組み」として機能している構造はまさに「つながらないことで、つながる」庭的構造の象徴である。
リングは物理的な境界でありながら、「つながり」を強制せず、各パビリオンの「部分的関与」や「距離」を許容する。この空間構成は、宇野が『庭の話』で描いた「新しい倫理の場としての庭」の実例と言える。
また、日本のシグニチャーパビリオンも一様ではない。「人新世」をテーマにした展示から、「いのち」を中心に据えた展示、サステナビリティ、伝統技術、未来技術を融合した試みなど、軸はあれど多様である。これらもまた、中心的思想に対する「周縁的な応答」として、庭的に散在していた。
評価やランキング、SNS的なバズを求めることとはまったく異なる次元で、人と人が感情を共有し、内発的な気づきを得ていく。この体験の中に、私は「庭」を見たのである。
教育・医療・地域社会における「庭」の応用的展望
これまで「庭」を抽象的に、あるいは思想的に論じてきた。しかし、庭の概念を真に有効なものとするためには、それが社会の現場でどう実装され得るかを検討する必要がある。教育・医療・地域社会を例に取り、「庭的な空間」がいかなる形で実践可能かを考察する。
1. 教育における「庭」
現代の教育現場は、評価と承認に過度に依存している。試験の点数、偏差値、内申点、進学実績。いずれも「承認の可視化」であり、子どもたちは常に「比較」の中に置かれる。その結果、「落ちこぼれ」と呼ばれる層が生まれ、学ぶ意欲を失う子どもたちも少なくない。
「庭的な教育」とは、評価から一時的に自由になる場の確保である。学習支援教室や探究学習の現場で、教師や大人が「結果を測らない空間」を提供すること。そこでは、子どもが自分のペースで関心を深め、時には休み、時には飛躍することが許される。このような「部分的関与」が可能な学習環境は、承認依存社会を生き延びるための「庭」として機能するだろう。
2. 医療における「庭」
医療は本質的に「評価の場」である。診断は正しいか、治療は有効か、数値は改善したか。そこには常に結果への圧力が存在する。しかし、患者にとっての「生きやすさ」や「納得感」は、必ずしも数値に還元されない。
「庭的な医療」とは、患者と医療者の間に「結果以外の時間」を共有することである。診察室での沈黙、病棟での雑談、在宅医療での“庭先の世間話”。これらは直接的に病を治さないが、患者の尊厳を守る上で決定的に重要である。つまり、庭的空間は「病を抱えながらも生きる」人々にとっての支えとなる。
3. 地域社会における「庭」
地域社会は「小サイズの共同体」の典型であり、同調圧力や承認の強制が最も色濃く現れる場所でもある。町内会やPTA、農村共同体では「役割」を果たさなければならないとされ、逸脱する者はしばしば排除される。
「庭的な地域」とは、役割や成果に縛られず、ただそこにいてもいい空間を意識的に作り出すことである。図書館、公園、カフェ、オープンスペース。特に「使い方を限定しない公共空間」は、庭的な性質を持ちうる。地域の人々がそこでただ過ごすことが許され、何も生み出さなくても排除されない。これこそが、承認社会をしなやかに生きるための基盤となる。
「庭」の倫理と未来への指針
宇野常寛が『庭の話』で提示した「庭」という概念は、単なる空間の比喩ではなく、現代を生きる私たちに必要な倫理的態度の提案である。本論で見てきたように、庭は「評価されること」「承認されること」から自由であり、人間が“何者か”でなくても存在できる空間である。それはSNSのような大規模プラットフォームでも、村落共同体のような小規模共同体でもなく、その中間にある「余白」としての空間である。
この「庭」の倫理は、次の三つの要素に要約できるだろう。
1.ズレを許容すること:庭は異なる時間や価値観を持つ存在を排除せず、むしろその“ずれ”を前提として成立する。現代社会において分断や対立を超えるためには、まずこの「ずれの肯定」が必要である。
2.部分的関与を認めること:すべてを管理せず、すべてをつなげず、必要な時に必要な関わりを持つ。これは共同体の同調圧力やプラットフォームの過剰な同期性への対抗である。
3.存在そのものを肯定すること:成果や役割を果たさなくても、ただ「そこにいる」ことを許す。これは教育、医療、地域社会において、とりわけ大きな意味を持つ。
この三つの倫理は、すぐに制度に落とし込めるような政策ではない。しかし、それは人々の態度や感覚の変化として、確実に現実を変えていく力を持つだろう。庭は「革命」ではなく「手入れ」に近い。大規模な転換ではなく、小さな日常の実践を積み重ねることで、社会全体に新しい息づかいをもたらすのだ。
筆者自身、EXPO2025での体験を通して、庭の萌芽を体感した。バラバラでありながら共存し、意味や一貫性よりも「存在の同時性」に価値を見出す空間。そこには、人類が未来に向けて必要とする共在の倫理が、すでに姿を現していた。
承認を求め続け、分断と競争に疲弊する現代社会において、「庭」という思想は、静かにしかし確実に、私たちを救う可能性を秘めている。ズレたまま、つながらなくても、私たちは共に生きることができる。その気づきを胸に、未来への小さな庭を、それぞれの場所で耕し続けることが、いま私たちに求められている。
